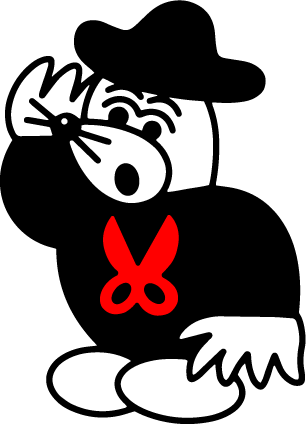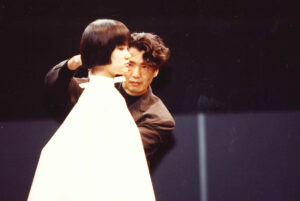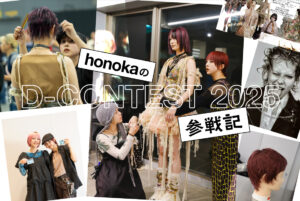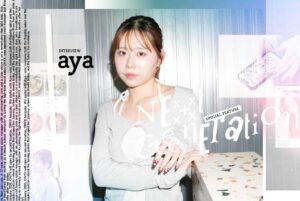技術のアップデート、どうしてる?
美容師ライター、操作イトウが日常の“サロンワークを乗り越えるヒント”を探るコラム連載第4回。毎日の営業で忙殺されていると、つい後回しにしてしまう“技術のアップデート”。情報があふれる今、どこで・どうやって・何を学ぶ?美容師にとっての“リスキリング”を考えます。
illust_モリスン
text_操作イトウ
トレンドの移り変わりが一層早くなっている昨今。
皆さんは定期的に技術のアップデート、できてますか?
日々の営業に振り回されて、ファッショントレンドや新しい薬剤に「付いていくのがやっと…汗」という方も少なくないかもしれません。
でもそう言ってる間に、いつのまにか自分が「時代遅れの美容師」になるかもしれないし、すでに時代遅れになっていることにすら、気付いていないかもしれませんよ。
情報も、収集する手段も
アップデートしよう

お客さまのオーダーするスタイルってマンネリ化しやすくないですか?
サロン勤めの方もフリーランスの方も、客層にもよりますが「街のヘアサロン」だと真新しいスタイルのオーダーは少ないですよね。
自分のお客さまでサイクルしている方ならなお、固定客が多くなるほど「前回と同じスタイル」をする場面が多くなって、新しいスタイルや薬剤の出番が回ってこない、ってことになりやすい。
とはいえ、世間では「リスキリング※」なんて言葉も聞かれます。「技術の更新」は、美容師にとってのリスキリングかもしれません。
※リスキリング: 時代に合わせて新しいスキルを学び直すこと。
あなたの毎回の情報収集源は、美容師さんのSNSですか?美容師仲間とのやりとり?それとも、ディーラー?
“雑誌・書籍・ディーラーから”は、最適?
特にサロン勤めの場合は、ディーラーさんから教えてもらうことが多いですよね。「最新の薬剤、使ってみませんか?」と勧められる情報は、確かで信頼できるものです。
とはいえ、それだけで“すべて”をまかなえるとは言えないかもしれません。
というのも、ディーラーさん自身が優秀で多忙な営業マンであることが多く、広いエリアを効率よくまわる必要があります。そのため、「このヘアサロンはこういうテイストが好き/あまり響かない」と、無意識に情報を選別している可能性もあるからです。
つまり、「ここのヘアサロン向け」というフィルターを通した情報であって、最新トレンドを網羅したものとは限らないかもしれません。
そしてそもそも、「ディーラーさんとお話する機会がない」というのも、美容師あるある。お店の材料担当でもないと「ディーラー→材料担当→自分」となるから、少ない情報しか得られていないかも。
加えて「業界誌や書籍から」という方は、だいぶ減ったのではないでしょうか。
特に信頼ある業界誌や書籍化されている情報は、ギュッと凝縮されているため、知識を深めるための貴重な資料です。
一方で、「読むのが苦手」「なに言ってるかわからない」という人も多いはず。
スピード感や手軽さに欠けるから、良くも悪くも「インスタントにかいつまんで」という方法ができないのが難点。
これら定番でオールドスタイルな情報収集は、今の時代に合った最善の選択とは言いきれないかもしれません。
SNSや動画で、スピード感と手軽さを確保

スピード感と手軽さにおいて対照的なのが、SNS。
勉強の意識はなくても、毎日何かしらのSNSをチェックしてるから、ほぼ受動的にでも吸収できてしまう。
最近はヘアサロンや個人に限らず、さまざまな業界の企業が「美容師向けメディア」として発信していますよね。YouTubeやInstagram、 TikTokを主戦場にしている方もいるし、ひとつ見るとレコメンドでどんどん出てくる。
ところで、あなたの職場ではDXは進んでいますか?急にビジネス用語を聞いて、アレルギーのように震えてしまう方も多いのではないでしょうか。
DX(デジタルトランスフォーメーション)については割愛しますが、そもそも美容師はアナログが染み付いて離れない仕事。
「指導」や「教育」は、従来と変わらないやり方をしているうちに、先取りしているヘアサロンはめちゃめちゃDX化しています。
例えば、アシスタントに向けた有料動画コンテンツを発信している企業もあります。
「職場の先輩から学ぶ」が当たり前だった頃とは違い、有名塾のように懇切ていねいに教えてくれる動画を見れば、全国どこでも同じ水準の教育ができます。
そしてスタイリストにとっても、「教え方を学ぶ」という意味でも、学び直しとしても、とっても参考になると思いますよ。
指導する立場での言葉がけのチョイスや理解度が深まって、頭が整理されるはずです。
横の繋がりに勝る勉強法はないかも?
個人的に技術のアップデートは、「外の美容師との意見交換」が一番影響を受けやすいのではないかと思っています。
僕自身、フリーランスとして数年働く中で自分の技術の考えが広がりましたし、色々取り入れて試す場面が増えました。
カットの仕方や薬剤の選び方など、テクニックの話は自分が教わってきたロジックと違ったりするから、新鮮に感じますよね。
そしてそれは、一緒に仕事をしているだけでも感じやすい。
カットする姿やカラーを選定している姿を見たり、カウンセリングに耳を傾けるだけでも、ライフハック法を見つけたかのようにハッ!とすることがあります。
外部との接点が少ないサロン勤めの場合は、情報収集が得意な同僚を頼るのがイイですよ。
情報が早い方って、いますよね。最新スタイルや薬剤、ファッション面でも、取り入れるのが上手なのはその人の才能だと思います。
もし「わたしは苦手だな」と感じているなら、その方の新情報を見逃さないようにしてみましょう。
セミナーには、動画じゃわからない“空気”がある
「勉強する」と言えば、セミナー。
サロン勤めなら会社単位でセミナーに参加したり、講師を招いて勉強会をする場面も多いと思います。
ですが、個人で足を運ぶ方は少数派なのではないでしょうか。正直、僕も数年行ってない…。開催日は火曜日がほとんどだし、休みの日はプライベートを優先したい、となりますよね。
ですが、特にサロン勤めの方にとっては「外の世界」を知る機会として有効だと思います。なぜなら、セミナーなら先述した「横の繋がり」の効果を疑似体験しやすいからです。
動画では見切れてよくわからないところや、深掘りされていなくて気になったところなど、工程の意図を説明してもらいながら実際にやっている姿を見れる、貴重な場です。
そして、その場で質問することができることも大きな利点。
せっかく出席するなら、質問のひとつやふたつ、手を挙げるつもりで行くといいですね。
フリーランスこそ「学ぶ仕組み」を作るべき

新しい技術は、新しいスタイルとともに訪れます。言わずもがな美容師はファッションが好き。
けれど、特にフリーランス美容師は「わたしのファッション感度」に頼るだけではなく、能動的に学ぶ「仕組み」と「マインド」を持った方がいいと思います。
というのも、皆それぞれ「好きなスタイル」があるから。「これがネクストトレンド」「大ブレイク中!」と言われたソレが、好みじゃないことだってありますよね。
すると、「私にはカッコよく見えない」「可愛く見えない」ということも起こりやすい。
だから美容師は、ベテランになるほど「新しいスタイル」に苦手意識を抱きやすいんじゃないかな、とも思います。
トレンドを受け入れられなくなったら、黄色信号
これが、「あのスタイルはカッコ悪いから、作りたくない」と感じるようになったら、黄色信号です。
これは「わたしのファッション感度」が高いからこそのジレンマでもあります。
そして最近は、特定のスタイルを推した「特化型」のスタイリストが増えました。が、トレンドの移行によってそれ自体の需要が縮小することもあり得ます。
積極的に新しいスタイルを取り入れていかないと、「わたしの推しスタイル」の需要は次第に無くなっていきます。
それって、どうすりゃいいの?
1から学び直しではなく、「再構築」しよう
「新しいトレンド」はそれまでの流れと“真逆”に見えやすいし、新しいスタイルはロジックが違ったりするもの。
僕もいちど陥ったことがありますが、新たに学び直す工程は「信じてきたことを壊す」作業にもなるので、苦労します。
でも、一度できるようになってしまえば次回もかんたんに壊す覚悟ができているから、結局、気持ちの問題が大きいかも。
この気持ちを切り替えるために、技術を「再構築」してみませんか?
「再構築」はファッション業界でよく使われる表現ですが、単に「わたしのファッション感度」をぶっ壊すんじゃなくて、目線を変えてみたり、新しいトレンドのイイところを抽出して、価値観をブラッシュアップする。そんな意味合いです。
こんな感じで変化をポジティブに捉えて、いろいろなことを肯定的に受け止めて、拒絶や否定をしないことが大事じゃないかな、と僕は考えてます。
トレンドは流れるもの。
次はどんなスタイルが求められて、どんな技術が必要になるのか、楽しみですね。

- TOP
- 今日を生き抜くヒント
- つながる
- 技術のアップデート、どうしてる?
TREND TOPIC
- TOP
- 今日を生き抜くヒント
- つながる
- 技術のアップデート、どうしてる?