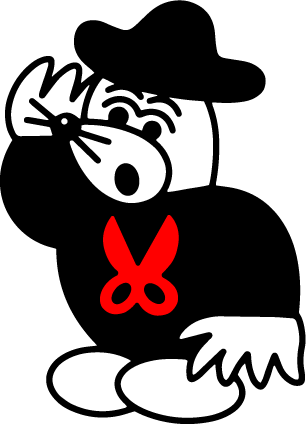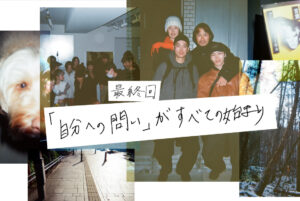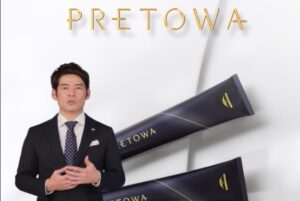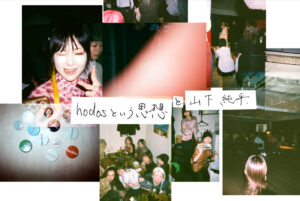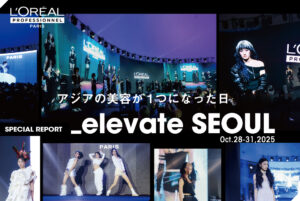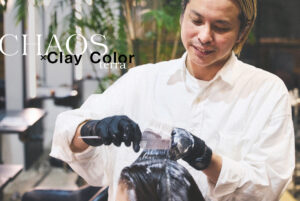What’s 「Beautify」

日本ビューティ・コーディネーター協会(以下、JBCA)が3月31日、「ビューティコンベンション」を開催した。同協会は、これまでサロンの接客やカウンセリング、物販を担う“ビューティ・コーディネーター”の育成に取り組んできた。
そんなJBCAが近年、「Beautify(ビューティファイ)」という新たなキーワードを掲げている。スタッフ・空間・提案力・サービスすべてにおいて『顧客の“ビューティをコーディネートする”』という考え方だ。
今回のイベントでは、このBeautifyをテーマに、JHAグランプリ受賞者による対談に加え、地域密着・ブランド型・シニア向けなど異なる視点から“これからのサロン”を語る3つの講演が行われた。
JBCAがいま、なぜBeautifyを掲げるのか?登壇者たちの言葉から振り返る。
登壇者プロフィール




JHAグランプリが語る
「作品づくりのその先」

唯一のセッション形式で行われた、JHA歴代グランプリ対談。
美容専門誌「BOB」の森井純子編集長がナビゲーターを務め、2023年受賞の飯笹豪さんと、2022年受賞の照屋寛倖さんが登壇。日々の積み重ねの中で見えてきた、美容のこれからについて語った。
“自分らしさ”はどう育つ?

クリエイションにおいて「自分らしさ」ってどうやって生まれるものなんでしょうか?

最初は「うまくつくりたい」「認められたい」という気持ちが強いと思います。でも、それだけだとどこか似たような作品になってしまう気がして。
やっぱり“自分が本当に好きなもの”を形にしていくことで、自分らしさって自然と出てくると思うんです。サロンワークでも、カラーが好きならカラーに特化するように、クリエイティブも“好き”が出発点だと思います

僕も最初から自分らしさがあったわけじゃないです。まずは憧れの人のデザインを3年くらい真似する。そこから少しずつ引き算して、自分らしい表現が見えてくる。
でも最近は、逆に“自分らしさを守りすぎないこと”の大切さも感じていて。「17%自分を捨てる」っていう意識で、新しい感覚を取り入れるようにしています。


おふたりにとって、クリエイションを通じた“Beautify”って、どういうことだと思いますか?

どんな仕事でも、作業で終わるのか、意思を持って向き合うのかで全然意味が変わってくると思います。たとえば鏡を拭くにしても、「このあと誰が座るのかな」と想像しながら拭く。毎日のなかに意思を持ち込むこと。僕にとってのBeautifyは、そういうことです。

僕にとってのBeautifyは、「クリエイションを続けること」そのもの。美容室からクリエイションがなくなってしまったら、デザインの未来が薄れてしまう。
だからこそ、生み出す行為を止めないことが、美容師を、サロンを、美しくしていく力になると信じています。
ファイブスター 佐久間正之
現場に光を届ける仕組みづくり

「美容師の社会的地位を、もっと高めたい」。そう語ったのは、ファイブスターグループ代表の佐久間正之代表。福島を拠点に、表参道やシンガポールを含む47店舗を展開し、新卒月給25万円を全国一律で導入するなど注目を集めている。
講演では、順調に見える拡大の裏で直面した、理念の浸透や人材マネジメントの難しさに触れた。「自分は美容師ではないから、技術で背中は見せられない。そのぶん、何を大切にするかを徹底的に考えてきた」と語るように、制度や仕組みで現場を支えるスタンスが一貫している。

「理念を共有できる環境を整えること。それが、今の自分の仕事」。経営の側から“光を届ける”姿勢が印象に残るセッションとなった。
EGAO 太田明良
シニア特化と美容の未来

「高齢化はネガティブな現象ではない。美容が果たす役割が、これからさらに広がっていく領域なんです」。そう語ったのは、「えがお美容室」を展開するEGAOの太田明良代表。ファッションスタイリストとして活動した後、シニア特化型のサロン事業に乗り出した。
日本の高齢化率は約29%。4人に1人が65歳以上という社会においても、ヘアサロンに通いづらさを感じる人は少なくない。太田氏は「ヘアサロンの客層で最も抜け落ちているのがシニア層」と語り、店舗づくりやスタッフ教育の再構築に取り組んできたという。

講演では、シニア層のニーズに応えるための空間づくりや接客、メニューの工夫などを具体的に紹介。「高価格帯を狙うのではなく、選ばれ続ける設計が大切」とし、高齢化社会における美容の可能性を提起した。
JBCAが描く“Beautify”の未来と
ABAとの連携

JBCAの板倉雄三理事長は冒頭、「JBCAは、美容師だけでなく、サロンに関わるすべての人の価値を高める団体として活動してきた」とこれまでの歩みを振り返り、「Beautify」というキーワードに込めた想いを改めて語った。
Beautifyを実現するには、接客やマネジメントだけではなく、技術との接続が不可欠だと語り、今後の展望として発表したのが、技術教育団体「ABA(アジアビューティアカデミー)」との連携だ。

ABAは全国の高単価・高付加価値サロンの美容師が理事・講師として参画する、技術を軸とした教育組織だ。アジア美容経済の発展を視野に入れ、技術教育の深化に取り組んでいる。渡邉弘幸理事長は「技術だけで終わらず、教育のあり方や現場での伝え方まで踏み込むことで、接客や組織と技術が分断されない現場づくりを目指したい」とコメント。JBCAとABAという異なる専門性を持つ団体がタッグを組むことで、ヘアサロンを“総合力”で支える動きが本格化していく。
講演の後には懇親会も
「Beautify」という理念が、サービスから技術へと領域を広げ、次のフェーズに差しかかっている。最後には懇親会も行われ、世代や職種を超えて語り合う光景が広がった。共通していたのは、“ヘアサロンをよりよくしたい”という想い。JBCAの活動に共感し、共に動き出す仲間はこれからも増えていきそうだ。
- 執筆者
- 木村 麗音
- Twitter : @kamishobo
- Instagram : @bobstagram_kamishobo